結論:金融知識を身に着けて自分の人生を生きよう!

・現在、40歳 妻妊娠中の3人家族になる予定
・2023年に警察官を退職
・契約社員としてバリスタFIRE中
・将来の目標は、子供が6歳になる頃にモルディブ旅行に家族で行く
保険代理店で働いて感じた自分のことを「他人任せ」にする思考
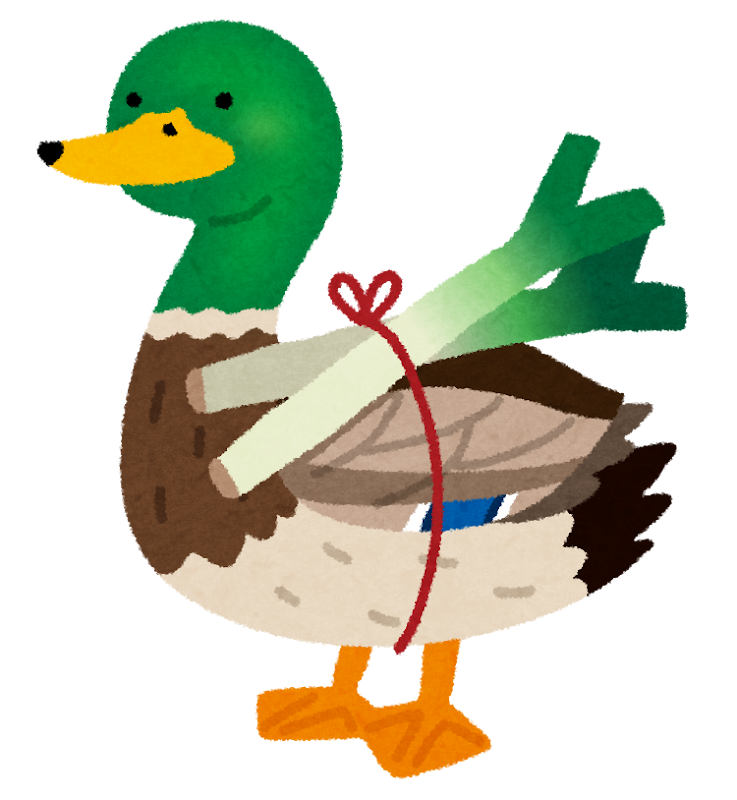
現在、40歳の元警察官が9月から保険代理店でバリスタFIREをしながら働き始めました。
そこで感じたのは、
従業員も顧客も、人生を他人任せにしている
という点でした。
お客さんからよく聞かれるのは、
「よくわからない」
「どうしたらいい?」
「病気になったら得するならどうするのがいいですか?」
といった言葉です。
正直、内心では「自分のことは自分で決めなさい!」と思ってしまいます。
しかも、月に5,000円から1万円以上の保険に加入することを当然のように受け入れている。
これは、金融知識の不足が引き起こす典型的な現象だと感じました。
まさにカモがネギを背負ってきている状態です。
金融知識を実践的に活用するのは難しい
保険代理店で働く従業員自身もまた、金融知識を活かせていないと感じています。
業務上、基本的な用語や仕組みを理解しているはずですが、それを「自分の資産形成」に結びつけていないのです。
金融の知識が「仕事用の知識」にとどまり、自らの生活や将来設計に反映されていない。
知識を実践として、活用することは非常に難しいと感じざるを得ません。
売っている個人年金保険の商品がどんなものに投資をして、資産を増やしているのか知らないと言われました。
保険加入が当たり前という考え方
さらに衝撃的だったのは、「月に5,000円から1万円の保険料を払うのが当たり前」という空気です。
もちろん保険はリスクヘッジの役割を果たしますが、
・なぜその保険に入るのか
・その支出が本当に必要なのか
を考えず、半ば惰性的に契約している人が大半です。
「なんのために保険に入るのか」をわからないまま加入している人が大半なのです。
金融知識を持っていれば「もっと効率的なお金の使い方がある」と気づくはずですが、多くの人はそこに思考を巡らせないまま毎月支払い続けています。
マネーリテラシーに関するデータまとめ

日本人の金融知識は世界的に見ても低い水準
日本では「利子計算・インフレ・リスク分散」に関する3問(通称 Big Three)にすべて正解できた割合は 36%程度 にとどまっており、先進国の中でも低い水準にあると報告されています。
📖 出典:Cambridge Journal of Financial Literacy and Wellbeing
金融リテラシー調査(2022年)
金融広報中央委員会「金融リテラシー調査(2022年)」によれば、金融知識の正誤問題(25問)の平均正答率は 47.2%。世代別では、18~29歳が 41.2% と特に低く、知識不足が顕著に表れています。
📖 出典:金融リテラシー調査 2022(知るぽると)
自分の金融知識に自信がある人はわずか
内閣府の調査によると、「自分の金融知識に自信がある」と答えた日本人は 12% に過ぎません。多くの人が「よくわからない」と考えており、行動にも結びついていないのが現状です。
📖 出典:政府広報オンライン
学校で金融を学んだ人はほとんどいない
「学校で金融知識を学んだ」と回答した日本人は 7% にとどまっています。これは教育課程に金融教育が十分に組み込まれていないことを反映しています。
📖 出典:政府広報オンライン
年代別のリテラシー差
MILIZE の調査(2023年)では、金融リテラシー問題で「13問以上正解」した割合は以下の通り
- 20代:38%
- 30代:54%
- 40代:65%
- 60代:82%
📖 出典:MILIZE 金融リテラシー調査2023
日本人のマネーリテラシーが低いと言われる理由

教育でお金を学ばないという構造的問
日本人のマネーリテラシーが低い最大の理由は、教育にあります。
義務教育でも高校・大学でも「お金の知識」を体系的に学ぶ機会がほとんどありません。
そのため、社会人になってから初めて「保険」「投資」「税金」に直面する人が多いのです。
しかしその段階ではすでに時間的余裕がなく、知識のアップデートが追いつかないまま金融商品を契約してしまう人が少なくありません。
自己決定よりも「お任せ文化」が根付いている
また、日本には「専門家に任せる」「みんなと同じにする」文化が根強く存在します。
保険加入や投資に関しても「よくわからないから任せる」「みんな入っているから安心」という心理が働きます。
しかし、自分のことを自分以上に考えてくれる人はいません。
原因自分論で行動しなければ、人生の主導権を他人に握らせてしまう事になりかねません。
金融機関に依存しすぎ
さらに問題なのは、金融機関に過度に依存する姿勢です。
「銀行が言うなら安心」「保険会社が提案するなら間違いない」と信じ込んでしまう人が少なくありません。
しかし金融機関は慈善事業ではなく利益を追求する組織です。
顧客の利益と必ずしも一致しない商品を勧めるケースもある。金融知識を持たずに依存すると、結果的に損をする可能性が高まるのです。
自己防衛としての金融知識の必要性

FIREや投資知識の欠如がもたらす未来
保険代理店で働きながら痛感したのは、FIREや投資に関する知識を持っている人がほぼ皆無だということです。
老後資金や資産形成に直結する重要なテーマなのに、誰も真剣に学ぼうとしない。
知識を持たないまま年齢を重ねれば、将来の選択肢はどんどん狭まります。
これは本人だけでなく社会全体にとっても大きな損失です。
自分で学び、活かす姿勢が豊かさを決める
金融知識は「知っている」だけでは意味がありません。
「学んだことを実際に活かす」ことが重要です。
たとえば節税、投資、保険の見直しなど、日常の選択に落とし込める人とそうでない人では、10年後に大きな差が生まれます。
自分で調べ、自分で判断し、責任を
持つ。この姿勢がなければ、どれほど良い教材や本を読んでも意味がないのです。
自己防衛ができる人とできない人の差
最終的に、人生の豊かさは「自己防衛力」で決まります。
他人に委ねる生き方をしている人は、不測の事態に脆弱です。
一方で、金融知識を備え、自分で判断できる人は環境に振り回されず、安定した生活を維持できます。自己防衛はお金に限らず、人生全般に通じる力だと言えるでしょう。
おわりに

保険代理店でバリスタFIREをしながら働いた1ヶ月間で、私は日本人のマネーリテラシーの低さを知りました。
ちなみになんだかんだ言っていますが、ゆる労働で働きながら自由に生活できるのはバリスタの良いところです。
保険代理店のシステムってこうなっているのか!とかお客さんってこういう人がいるのか!など毎日、新鮮です。
来年、生まれる子供のために頑張ります♪



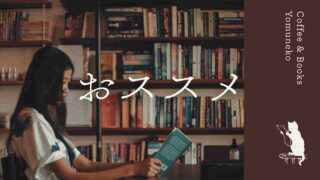
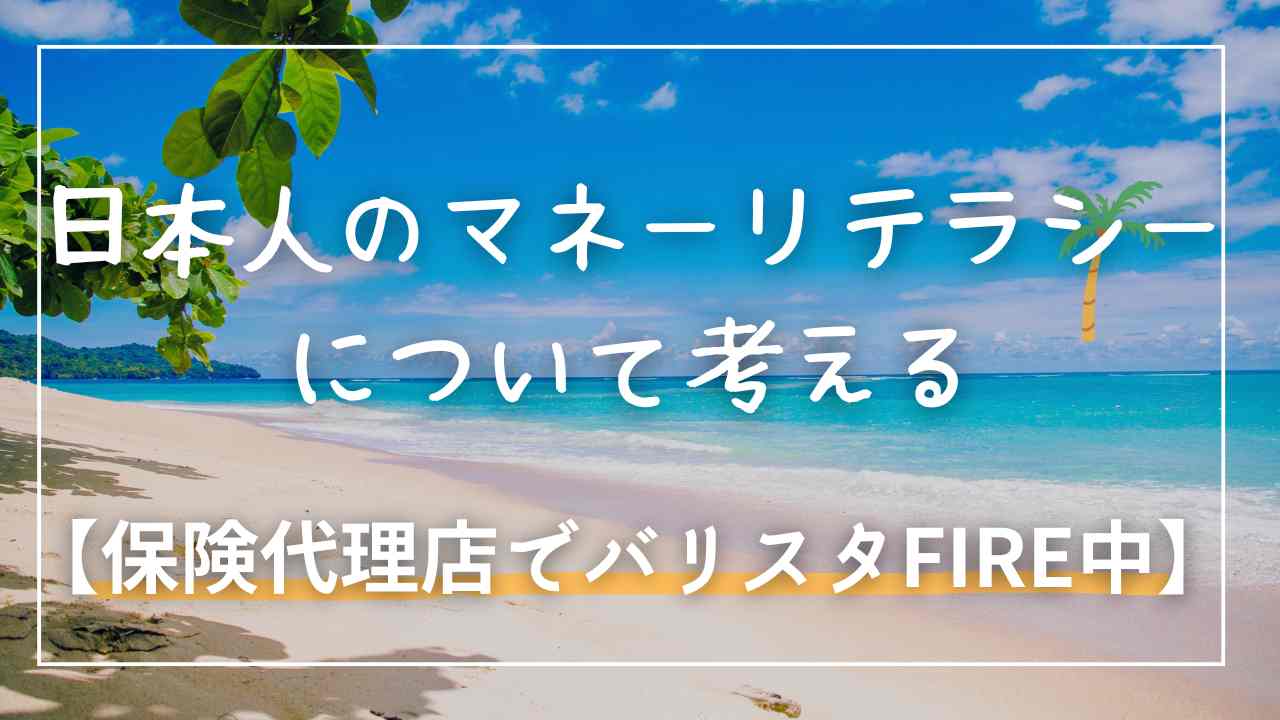
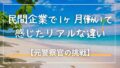
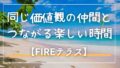
コメント